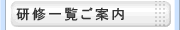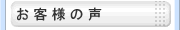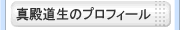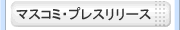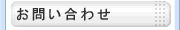|

| このページでは私、真殿道生の研修に対する基本的な考え方をお伝えしたいと思います。 |


| 考え方と基本行動 |
例えば高価な商品を買うとき、自分の目で見、手でもってみる、あるいは体験してみることは、ショッピングの常識です。つまり必ず現物を事前に確かめて、十分に納得して購入するわけです。
次に視点を変えて商品の側から客を見るとどうでしょうか。例えば高価なブランドスーツでも、身につける客が新入社員だったりすると周囲は違和感を覚えるでしょう。共感されないかもしれません。客と商品には、相応しい相性というか自然な調和が必要なわけです。
客と商品の関係は、研修上のクライアントと講師の関係に似ています。クライアント(=顧客)も事前に十分な納得がほしいはずです。しかし研修は、
|
 |
| 体験してみないと本当の価値がわからない |
性格のもの。しかも決して安い買い物ではありません。慎重になるのは当然です。
ベイスマネジメントでは講師が営業の役割も兼ねて直接ヒアリングをし、顧客に
|
| 持論と自己主張 |
をします。つまり講師をしっかり見てもらうこと、持論に同意できるかを判断してもらう
ことを最優先しているのです。基本的なベクトルが合うかどうか、しっかりキャッチしてもらうのです。講師はそこで顧客の現場を踏み、さまざまな情報を聞き出すことができます。
いっぽうせっかく良い企画の研修であっても、受講者とのミスマッチがあると効果を発揮しません。受ける人が本当にこれがいま自分に必要なのだ、という思いや意識が絶対に欠かせないわけです。これが
|
| 顧客のニーズに合う |
ということだと思っています。ニーズはあるのではなく、つくるもの、気づかせるものです。
受講者自身がそのニーズに気づいていないことも少なくありません。そこでいま、この |
| 研修をする意味や目的 |
を初めにしっかり理解してもらうことが絶対に必要です。相性の擦りあわせをキチンと行なうことが、とても重要だと思っています。
研修の成否を左右するひとつの重要な要素が |
| 講師の質 |
です。私は大手教育機関にいたときにそのことを嫌というほど痛感しました。同じカリキュラム、同じプログラムを実施しているにもかかわらず、受ける側の印象やインパクトがまったく違うのです。
|
 |
| 誰が話すか、 |
誰がその仕事を担当するか、が決定的に重要だったのです。しかし大手機関でも実際“できる講師”は一握りで、そういう人はなかなか登板させません。いざ、というときの為に“だしおしみ”するのです。
自分の顧客には最大のサービスをしたい、という自己願望は大手機関では実現できませんでした。他の事業もそうですが、特に
|
| 研修は「人」が最大の資産 |
です。講師はプロである必要があります。プロというのは一回一回が勝負です。
仕事をしてもしなくても給料が保障されるサラリーマン根性では勤まりません。
私は教育会社をつくるときに講師についての妥協だけは絶対にすまい、と
心に決めました。クライアントが最も気にかけることは「成果」です。研修における成果とは何か、何がどうなればよいのか。それが職場での「行動変容」に繋がるか、また繋げるための仕組みは…そこまでの情熱と自信、専門性、そして何よりも
|
| 実績 |
があること。
そういうキャリアで、団体に所属せずに腕一本で開業しているコアな人たち。
その人の中から、人物をこの目で確かめ、ネットワークを築いてきました。
質には絶対の自信を持っています。
講師は「先生」ではありません。
|
 |
| 講師は「商品」 |
です。その商品価値を高めていく努力を永遠に続けること。
それこそ、我々に課せられた使命だと考えます。
|
|
| COPYRIGHT(C)2006 ベイスマネジメント ALL RIGHTS RESERVED.
|
|